TEA FOLKS27 駄農園 高塚貞夫さんのご紹介
- Masayuki Mahara
- 2023年8月26日
- 読了時間: 6分
TEA FOLKS(ティーフォルクス)は2カ月に一度、2茶園のプレミアム和紅茶を茶園のストーリーとともにお届けする定期便サービスです。
定期便価格で最新版をご希望の方はこちらからお申込みください。

1. 駄農園「くらさわ」の特徴

「くらさわ」は「やぶきた」の自然交雑実生群中から選抜され、1967年に登録されました。
農林登録こそされていないものの、豊かな香気やしっかりとした苦渋味など特徴のある品種で、後に開発される「香駿」の母品種でもあります。
駄農園といえば、「藤かおり」とその兄弟品種である「森1号」「森2号」のイメージが強いですが、今号では「くらさわ」をご紹介いたします。
「くらさわ」は比較的、単一品種で見かけることの少ない品種ですが、とても個性的な品種です。
今回お届けする「くらさわ」はもともと、他の方が経営していた茶畑を駄農園が引き継ぎ、栽培しています。
1960年代に初めてこの畑に植えられ、その当時は今の畑とは様相が異なり、駄農園が畑を引き継いでから乗用摘採機を入れられる形に整えたそうです。
駄農園では現園主の貞夫さんが本格的に紅茶づくりに乗り出してから、「くらさわ」を紅茶に用いるようになりました。
それ以前は長らく深蒸し茶のみに用いており、紅茶以外にも釜炒り茶や白茶に回すようになったのはここ最近のことだそうです。
そして本ロットは去年以前と製法を変えており、具体的には乾燥工程での中揉機の温度を高く設定することで、以前よりも早く茶温が上がるようにしています。
そのためか、昨年以前のものと大きく雰囲気が異なる仕上がりとなっています。
本ロットの「くらさわ」は品種特徴であるハーバルさや、草原のような爽やかさのある香りが特徴的です。
一方でボディ感は意外としっかりとしており、またキレのある心地よい渋みや華やかな余韻が続く満足度の高い逸品です。
ホット、アイスともにオススメですが、是非ストレートで味わってみてください。

2. 駄農園のはじまり
現園主の高塚貞夫さんは3代目になります。初代園主である貞夫さんの祖父、高塚吾郎さんは約70年前の1952年に本家から独立して、牧之原の地で茶園経営を始めました。
この土地における茶の歴史は静岡県内でも比較的新しく、明治初期頃、武士階級の人々によって切り開かれてきました。
しかしながら、それ以前までに茶業が興らなかったのも頷けるくらい、県内の他の地域に比べて農業には向いていない土地であったそうです。
そのためか、かつては静岡茶の中でも牧之原のお茶にはネガティブな印象があったらしく、初代園主の吾郎さんはこれを払拭しようと様々な試みに取り組みました。
吾郎さんは様々な製法を試すだけでなく、多くの品種を用いて牧之原の土壌にあったものを見つけようと、試行錯誤を繰り返しました。
色々な品種を試すうちに、その数は増え、最大で50以上もの品種を植えていたこともあるそうです。
このとき吾郎さんは経営を顧みることなく、自茶園の品種選定など研究改善に没頭していたため、友人の農家から「お前は駄農家だな」と言われたそうです。
しかし、吾郎さんはこの「駄農」という言葉を気に入り、そのまま茶園名にしてしまいました。

3. 駄農園のお茶づくり
駄農園では、お食事と一緒にお茶をいただくことを考えて、スッと体に入っていくようなお茶づくりを目指しています。
また栽培品種も多く、流石に初代の50余品種には及ばないものの、現在でも13の選び抜いた品種を育てています。
中核を成すのはやはり「藤かおり」、後述する「森1号」「森2号」、その他にも「やぶきた」「かなやみどり」「するがわせ」、そしてこの度お届けする「くらさわ」など静岡系の緑茶品種が目立ちます。
そして紅茶品種としては「べにふうき」や「からべに」などの栽培も行っています。
種類としては主に緑茶と紅茶ですが、白茶もわずかながら生産しているそうです。
緑茶については、牧之原茶の定番「深蒸し茶」よりもさらに長い時間かけて蒸らす「特蒸し茶」と静岡県内では珍しい「釜炒り茶」の二種類を扱っています。
紅茶と釜炒り茶の生産は二代目園主の父、高塚孝さんが始めました。
孝さんは香りのするお茶や中国茶が好きだったため、香りがより際立つ紅茶や釜炒り茶の生産を趣味で行っていたそうです。

この時は香りに特徴のある品種「かなやみどり」のみを用いて紅茶を作っていました。
この頃、父の孝さんから貞夫さんへと世代交代が行われ、貞夫さんが紅茶と釜炒り茶の生産を引き継ぎました。
紅茶づくりを引き継いだ貞夫さんは、香りや余韻のある紅茶を志しています。
そのため施肥の量を少なくして、茶の酸化発酵を阻害することなく、香りのポテンシャルを最大限に引き立たせます。
そして、この駄農園の紅茶で特徴的なこととして、発酵度合いの低さがあげられます。
発酵度合いの低い紅茶はとても爽やかな香りを放ち、華やかな印象を纏いますが、その分萎凋時間や発酵止めのタイミングなどには常に集中力が必要とされるそうです。
この製造過程で生まれてくる甘く華やかな香りを楽しみに、高塚さん夫妻は製茶に励まれています。
また駄農園の商品パッケージなどに登場するユニークなキャラクター「お茶うさぎ」は娘さんの手がけるイラストで、多くのお客様に親しまれています。
こうして「かなやみどり」から始まった駄農園の紅茶づくりは、代々に渡って引き継がれ、現在では「藤かおり」そして「くらさわ」など駄農園を象徴する商品をいくつも創出するようになりました。

4. 「藤かおり」の誕生と「森3兄弟」
1996年に品種登録がされた「藤かおり」ですが、品種化に至るまでの最終候補にあと2つの選抜種が挙げられていました。
そのため最終的に「藤かおり」が選抜されるまでは、開発者の森薗氏にあやかって、それぞれに「森1号」「森2号」「森3号(藤かおり)」の名前がつけられました。
これらは駄農園を含む幾つかの茶園で試験栽培が行われていましたが、「森3号(藤かおり)」が最終選抜され品種登録されると、他の2種類は数を減らしていき、駄農園に残るのみとなりました。
3種類とも共通してアッサム種の系譜を感じさせる香りや力強い味わいが特徴的ですが、一つ一つ微妙に個性が異なるのが面白いところです。

5. 牧之原茶の始まり
前述した通り、牧之原茶の歴史は他の静岡県内の産地に比べるとやや新しいです。
牧之原は台地になっているため、昔から水を得るのが難しく、そのため土地は荒廃して農民すらも目を向けない土地となっていたようです。
この土地が茶畑に利用されるきっかけとなったのは、1867年に徳川家第15代将軍の徳川慶喜が隠居して、駿府へ移り住んだことでした。
この時、慶喜の側近である「精鋭隊」(のちの「新番組」)も共に駿府へ移住します。
しかしながら、移住してすぐの1869年には大政奉還が実現し、幕府が崩壊すると「新番組」は職を解かれてしまいます。
そんな彼らが新たに見つけた仕事が茶畑の開墾だったようです。
かつて「新番組」の隊長を務めた中條景昭は、他の武士たちをまとめ上げ、晩年までこの土地の茶業に貢献しました。
その後、彼らの意志を継ぐように現れた戸塚富蔵や今村茂兵衛らによって「深蒸し茶」の製法が確立されたことにより、今日の牧之原茶のブランドが成立します。
(参照:牧之原市 「牧之原お茶物語」)
近代日本の幕開けと共に、茶業が切り開かれた牧之原では今や広大な茶畑が一望できます。
静岡のお茶どころを巡る際には、是非歴史にも思いを馳せながら巡ることをお勧めいたします。

TOKYO TEA BLENDERSではティーインストラクターの知識をお伝えする無料メルマガTEA FOLKS通信で紅茶のおいしいいれ方やペアリング、歴史など幅広い情報をご紹介しています。ぜひご覧ください。


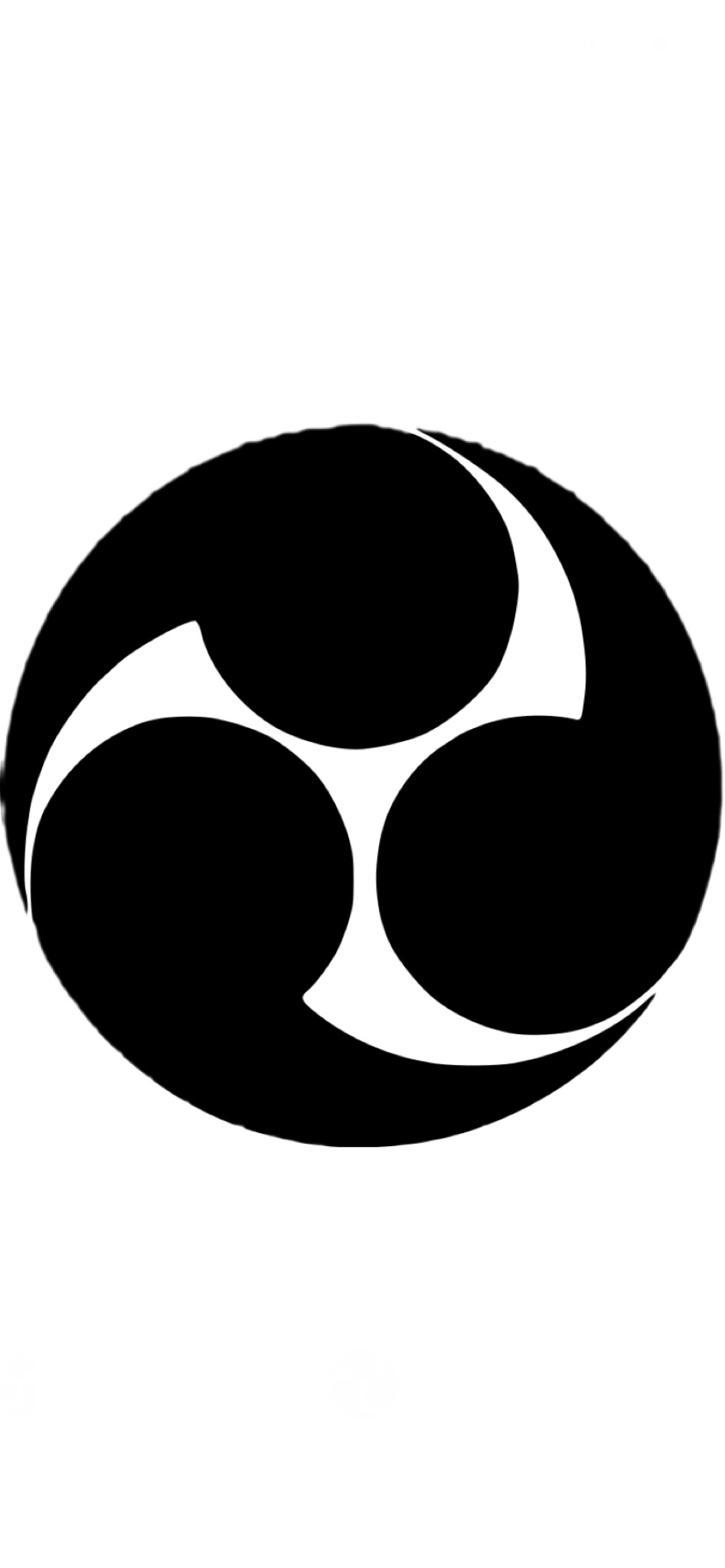



コメント