TEA FOLKS29 牧之原山本園 山本守日瑚さんのご紹介
- Masayuki Mahara
- 2023年10月28日
- 読了時間: 7分
TEA FOLKS(ティーフォルクス)は2カ月に一度、2茶園のプレミアム和紅茶を茶園のストーリーとともにお届けする定期便サービスです。
定期便価格で最新版をご希望の方はこちらからお申込みください。

1. 牧之原山本園「あかね」の特徴

今回お届けするのは牧之原山本園のオリジナル「あかね」夏摘みです。
本ロットのものは7月下旬に摘採、製茶を行い、9月初旬に火入れ仕上げを施しました。
現園主の山本守日瑚(やまもともりひこ)さんは、4年前に知人から台湾に由来のある茶樹を譲ってもらったそうです。
台湾系という事で香りの良い物になるのではないかと思った守日瑚さんは自園に植えることを決めて「あかね」と命名しました。
牧之原山本園では、この「あかね」を用いて主に紅茶と烏龍茶の製造を行っています。
5年ほど前から農薬や化学肥料の使用をやめ、今年から完全に農薬・化学肥料不使用栽培された区画の「あかね」は、その土地の栄養と茶樹本来が持つ力強さを発揮して、豊かな風味を湛えた仕上がりとなりました。
トップノートは黄桃のような甘く優しい果実香が漂い、口に含むと花のような香りが鼻腔を抜けていきます。
また牧之原山本園の最大の特徴といっても過言ではない「焙煎」が施されており、この工程によって甘く、円やかな味わいを実現しています。
そして牧之原山本園のもう一つの特徴とも言える萎凋時の「攪拌」工程では、萎凋中の茶葉を掻き揚げるように動かすことで、茶葉の香りを更に引き出し、この紅茶が持つ華やかさを生み出しています。
和紅茶でありながらも異国情緒漂う「あかね」を是非一度、ご賞味ください。
2.牧之原山本園のはじまり
牧之原山本園のルーツは明治時代まで遡ります。
牧之原は幕末期に江戸から来た侍たちによって開拓された茶産地です。

1867年に大政奉還を迎え、江戸幕府が崩壊すると、15代将軍の徳川慶喜公は駿府へ戻る事を決意しました。
この時、勝海舟の提案により元幕臣の中條金之助景昭をはじめとした慶喜公の側近の侍たちは、護衛団として精鋭隊を組織して、ともに駿府へ向かいます。
牧之原山本園の歴史も侍開拓団にあり、同家のご先祖様は代々徳川家の御殿医を勤めていました。
そして同園の初代にあたる山本惟鎮さんもまた、慶喜公の護衛を務める精鋭隊の1人として牧之原にやってきました。
しかしながら、新たに幕を開けた時代では精鋭隊の侍たちは、刀以外の方法で稼ぐ必要がありました。
そこで、かつては幕府直轄の天領であり、1425haもの規模があった牧之原台地で農業を営むようになります。
ただ残念なことに、当時の牧之原台地は水利が乏しく地元の農家にも手をつけられないような荒野でした。
そのため旧幕臣たちは土地の開墾から着手しなければならず、牧之原が今の形に至るまでに想像を絶する苦労がありました。
1869年、実際に中條金之助景昭や山本惟鎮さんら精鋭隊の元幕臣たちは徳川家達の許可をもらい、牧之原荒野の開墾に着手しました。
この時、日本の主要輸出品目であった生糸や茶に目をつけた勝海舟らの提言により、茶の生産を決め、牧之原荒野の開墾作業を進めて行きます。
しかし牧之原荒野の開墾はあまりにも厳しいものとなり、10年ごとに侍開拓団の数は半減していきました。
初めは250名いた侍開拓団は最終的に50名程度まで減少し、その中でも最後まで残った専業農家は山本家のみとなりました。
人員が減少していく中、1877年に開墾地の面積は500町歩に及び、牧之原荒野開墾の悲願は達成されます。
これを讃えて中條金之助景昭をはじめ、旧幕臣の名は大井川流域の初倉地区に鎮座する石碑に刻まれているそうです。
幕末や明治維新と聞くと、昔話のように思えるかもしれないですが、守日瑚さんにとってはそう遠い出来事ではありません。

山本惟鎮さんが最初の侍開拓団としてやってきた直後に生まれた子であり、守日瑚さんの曽祖母にあたるノブさんは91歳まで生き、当時2歳だった守日瑚さんがノブさんに乳母車を押してもらっていた記憶を今でも憶えているそうです。
開墾達成から時が経ち、大正昭和と2つの時代を乗り越えると牧之原山本園を悲劇が襲います。
第二次世界大戦および太平洋戦争の勃発です。
戦争の影響はこの地にも波及し、1942年に牧之原台地の茶畑は大井海軍航空隊に没収され、その上に飛行場を建てられてしまいました。
戦時中は苦しい思いをしながらも、漸く先の大戦が終結すると、開拓茶農協を発足し、58名の作業員で飛行場の滑走路を引き剥がし、再度開墾を開始しました。
2度の過酷な開墾を経て、牧之原山本園は現在の姿に至ります。
また守日瑚さんは現在開拓茶農協の理事を勤めています。
こうした経緯から先祖への畏敬と、牧之原の土地に魂の繋がりを感じている守日瑚さんは、茶園名にその名を付け、英語名では"SAMURAI Tea Farm"と表記するようになりました。
3. 牧之原山本園のお茶づくり
牧之原山本園では、他の牧之原茶同様に深蒸し茶よりも更に深く蒸した「特蒸し茶」を先祖代々生産していました。
現在では茶業に専念している牧之原山本園ですが、先代の頃までは養豚業や養蚕業も営んでいたそうです。
栽培している品種は「あかね」をはじめ、「べにふうき」や「くらさわ」「香駿」「あさつゆ」など多岐にわたります。
5代目となる現園主の山本守日瑚さんは、静岡大学を卒業した後にアメリカで2年間の農業研修を行い、知識や経験を蓄えました。

帰国して直ぐに就農した守日瑚さんは茶業の他に、アメリカで身につけた英語力を活かして、茶農家と塾講師という二足の草鞋を履いた生活を35年間も継続していたそうです。
特に若い頃は、塾の仕事が終わってから1〜2時間程度の仮眠を取ると、夜の製茶当番をこなし、茶刈りに出るというハードな生活を送っていました。
そんな生活を続けながらも、守日瑚さんは2009年に紅茶の製造を始めます。
きっかけとなったのは当時流行していた、抗アレルギー商品としての「べにふうき」だそうです。
同園で栽培していた「べにふうき」は、元来紅茶に適性のある品種として開発されていたため、守日瑚さんは興味本位で「べにふうき」を用いた紅茶製造に乗り出しました。
その後、静岡県掛川市で開催された国産紅茶シンポジウムにおいて、村松二六さんや益井悦郎さんなどの先駆者による紅茶に感銘を受けていたことで、紅茶製造の深部に歩を進めることとなったそうです。

そんな守日瑚さんが作る紅茶の最大の特徴はなんといっても「焙煎」です。
今でこそ目にする機会の増えた「焙煎」紅茶ですが、守日瑚さんは2015年から取り組んでいます。
そして牧之原山本園の紅茶に欠かせない、もう一つの特徴が萎凋時の「攪拌」工程です。
攪拌工程は萎凋時の香りを豊かにし、焙煎工程は熱による茶成分の変化を引き起こすことで、果実のような香りと円やかな甘味を引き出すことを可能にしています。
国産の紅茶用品種「べにふうき」や牧之原山本園のオリジナル品種「あかね」などを用いて、上記の手法で作る「ほうじ香り紅茶」は国内の品評会でも数多くの賞を獲得しました。
そして2018年からは化学肥料と農薬を使用せずに栽培しており、品種本来の個性が更に際立つものとなっています。
4. 科学的データに基づいた技術の継承
牧之原山本園のシグネチャーとなる「焙じ香り紅茶」の製造は、最近まで守日瑚さんの感覚に頼る部分が大きかったそうです。

守日瑚さんは2015年から「焙煎」に取り組み始め、技術向上のために試行錯誤を楽しみながら繰り返してきました。
どのようにすると理想の紅茶を作れるのかを考える事が楽しかった守日瑚さんは、研究所の先生を捕まえてたくさん質問したこともあったそうです。
そのおかげで「焙煎」の方法は一年ほど前から定番化し、今日では科学的手法でその条件を分析しています。
これには守日瑚さんの感覚によって生まれた技術をデータ化する事で、昨年就農した息子さんをはじめ、牧之原山本園の製茶条件において誰にでも再現可能なものとする目的がありました。
5. オリジナル商品「あかね」の由来

夕方になると牧之原台地に差し込む夕焼けは、西の空を茜色に染めて深緑色の茶園と素晴らしいコントラストを織り成し、日中の畑仕事で疲れた守日瑚さんの心をいつも癒してくれるそうです。
守日瑚さんはその鮮やかな茜色と紅茶の紅色を重ねてイメージして、このオリジナル商品「あかね」の由来となりました。

TOKYO TEA BLENDERSではティーインストラクターの知識をお伝えする無料メルマガTEA FOLKS通信で紅茶のおいしいいれ方やペアリング、歴史など幅広い情報をご紹介しています。ぜひご覧ください。


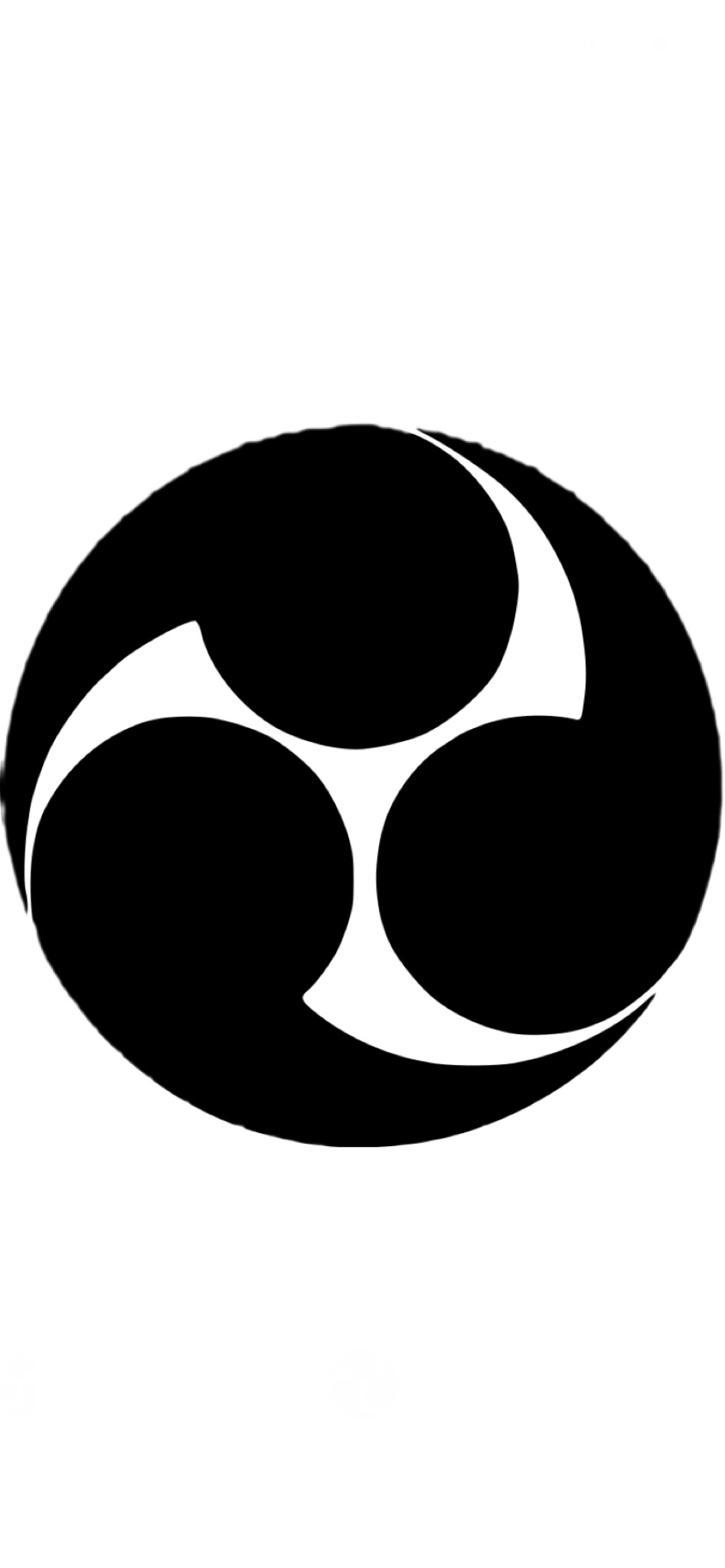



コメント